
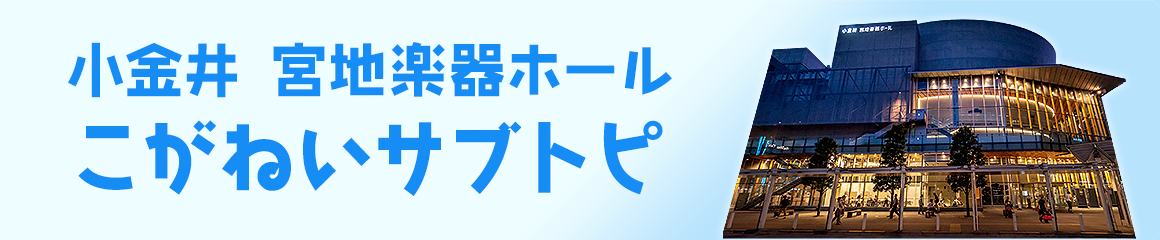
市内の小学生が「こがねいジュニア特派員」として鑑賞レポートを書いて発信!
ぜひご覧ください。(原文のまま、書き起こしています。)
***************************************
落語 梅にうぐいすの会
小金井市立小金井第二小学校 4年 林田和佳南
三遊亭歌きちさん
[演目] たらちめ
しゃべり方がハキハキしていて、子供でもききとりやすかったです。
全く知らない落語だったけれど内容がつかみやすかったです。
春風亭昇々さん
[演目] お面接
ちゃんと子供とお母さんとで声や背を変えて演じていて、すごいと思いました。
こんな現代的なおもしろい落語もあるんだと思いました。
柳家花緑さん
[演目] 時そば
一人で二人の人を演じていたので、むずかしそうだなぁと思いました。
同じそばでもふといそばで食べ方を分けて演じていました。(驚)
古今亭文菊さん
[演目] 権助提灯
文菊さんのドアをコンコンとたたくシーンが、とても上手で、まねしてみたくなりました。(笑)
どこに行ってもかえれと言われていて、わらってしまいます。
五街道雲助さん
[演目] 妾馬
この五人の中で一番長い落語でした。
一目ぼれするという設定が面白くて、早く続きが知りたい、と前のめりになりそうになってきいていました。
個人的におもしろかったランキング1位はー?
おっとっと!!落語の前に花緑さんが
「1番を決めるってことは2番、3番があるからあきられるんだ」
と言っていたので、書きません!(決めません!)
感想
元々、この「小金井ジュニア特派員」に入った理由は、日テレ4チャンネルでやっている、「笑点」という番組が好きで、落語を観てみたいと思ったからです。なので、生で初めて落語を観れてうれしかったです!
小金井第二小4年
寿限無 寿限無 五劫のすりきれ
海砂利水魚の水行末雲来末風来末
食う寝る処に住む処
藪ら柑子の藪柑子 パイポパイポ
パイポのシューリンガン
シューリンガンのグーリンダイ
グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの
長久命の 長助 こと 林田和佳南
(公演写真:藤本史昭)
***************************************
「笑点」が好きという林田さん。
演目のポイントや、落語家さんの動きがとても分かりやすいです。
自分のお名前の前に落語の寿限無を持ってきたり、
ランキングの話も洒落が効いていて、とても楽しいレポートです。
★スタッフによるイベントレビューは【こちら】
![]() 最新の書き込み
最新の書き込み
【こがねいジュニア特派員レポート vol.27】
第26回 こがねい落語特選 <新春>梅にうぐいすの会
【こがねいジュニア特派員レポート vol.26】
第26回 こがねい落語特選 <新春>梅にうぐいすの会
【こがねいジュニア特派員レポート vol.25】
挾間美帆 & 滝 千春 project MaNGROVE
【こがねいジュニア特派員レポート vol.24】
挾間美帆 & 滝 千春 project MaNGROVE
【こがねいジュニア特派員レポート vol.23】
フラメンコギター・デュオ 徳永兄弟 ライブ with パルマ&ダンス・カンテ
【こがねいジュニア特派員レポート vol.22】
フラメンコギター・デュオ 徳永兄弟 ライブ with パルマ&ダンス・カンテ
【こがねいジュニア特派員レポート vol.21】
はけの森美術館 展覧会《中村研一とモダニズム》
【こがねいジュニア特派員レポート vol.20】
はけの森美術館 展覧会《中村研一とモダニズム》
【こがねいジュニア特派員レポート vol.19】
はけの森美術館 展覧会《中村研一とモダニズム》
【こがねいジュニア特派員レポート vol.18】
宇崎竜童 弾き語りLIVE 2025 ~JUST GUITAR JUST VOCAL~
![]() 月別アーカイブ
月別アーカイブ
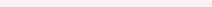 |
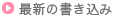  |
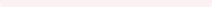 |
 |
|
〒184-0004
東京都小金井市本町6-14-45 TEL: 042-380-8077 FAX: 042-380-8078 開館時間: 9:00 ~ 22:00 受付時間: 9:00 ~ 19:00 休館日: 毎月第2火曜日および第3火曜日(祝日の場合はその直後の平日) / 年末年始 / 保守点検日 |
 |
|
【こがねいジュニア特派員レポート vol.27】 第26回 こがねい落語特選 <新春>梅にうぐいすの会 |
26. 02. 06 |
市内の小学生が「こがねいジュニア特派員」として鑑賞レポートを書いて発信!
ぜひご覧ください。(原文のまま、書き起こしています。)
***************************************
落語 梅にうぐいすの会
小金井市立小金井第二小学校 4年 林田和佳南
三遊亭歌きちさん
[演目] たらちめ
しゃべり方がハキハキしていて、子供でもききとりやすかったです。
全く知らない落語だったけれど内容がつかみやすかったです。
春風亭昇々さん
[演目] お面接
ちゃんと子供とお母さんとで声や背を変えて演じていて、すごいと思いました。
こんな現代的なおもしろい落語もあるんだと思いました。
柳家花緑さん
[演目] 時そば
一人で二人の人を演じていたので、むずかしそうだなぁと思いました。
同じそばでもふといそばで食べ方を分けて演じていました。(驚)
古今亭文菊さん
[演目] 権助提灯
文菊さんのドアをコンコンとたたくシーンが、とても上手で、まねしてみたくなりました。(笑)
どこに行ってもかえれと言われていて、わらってしまいます。
五街道雲助さん
[演目] 妾馬
この五人の中で一番長い落語でした。
一目ぼれするという設定が面白くて、早く続きが知りたい、と前のめりになりそうになってきいていました。
個人的におもしろかったランキング1位はー?
おっとっと!!落語の前に花緑さんが
「1番を決めるってことは2番、3番があるからあきられるんだ」
と言っていたので、書きません!(決めません!)
感想
元々、この「小金井ジュニア特派員」に入った理由は、日テレ4チャンネルでやっている、「笑点」という番組が好きで、落語を観てみたいと思ったからです。なので、生で初めて落語を観れてうれしかったです!
小金井第二小4年
寿限無 寿限無 五劫のすりきれ
海砂利水魚の水行末雲来末風来末
食う寝る処に住む処
藪ら柑子の藪柑子 パイポパイポ
パイポのシューリンガン
シューリンガンのグーリンダイ
グーリンダイのポンポコピーのポンポコナーの
長久命の 長助 こと 林田和佳南
(公演写真:藤本史昭)
***************************************
「笑点」が好きという林田さん。
演目のポイントや、落語家さんの動きがとても分かりやすいです。
自分のお名前の前に落語の寿限無を持ってきたり、
ランキングの話も洒落が効いていて、とても楽しいレポートです。
★スタッフによるイベントレビューは【こちら】
|
【こがねいジュニア特派員レポート vol.26】 第26回 こがねい落語特選 <新春>梅にうぐいすの会 |
26. 02. 06 |
市内の小学生が「こがねいジュニア特派員」として鑑賞レポートを書いて発信!
ぜひご覧ください。(原文のまま、書き起こしています。)
***************************************
小金井市立小金井第三小学校 2年 秋田野晴
[らくごかさんのこと]
五人のらく語かさんがいました。
三ゆうてい歌きちさん
春風ていしょう々さん
やなぎ家花ろくさん
古今てい文ぎくさん
五かい道雲助さん
の五人です。
[ぶたいについて]
ぶたいで、らく語かさんがかわると、一回一回ざぶとんをひっくりかえしていました。
おきゃくさんの中に子どもはあまりいませんでした。
[おもしろかったらくご]
ときそばが1番おもしろかったです。せんすのようなものではしをひょうげんしていました。あと、たべる声もすごかったです。
[かんそう]
むずかしいことばでちょっとよく分からなかったけどはじめてらく語を見ていいけいけんになりました。また、見てみたいです。
(公演写真:藤本史昭)
***************************************
見てワクワクするようなレポートを作成してくれた秋田さん。
真ん中の落語家さんも可愛いです。
落語をまた見てみたいとのこと、ぜひホールに遊びにきてくださいね。
★スタッフによるイベントレビューは【こちら】
|
【こがねいジュニア特派員レポート vol.25】 挾間美帆 & 滝 千春 project MaNGROVE |
26. 01. 29 |
市内の小学生が「こがねいジュニア特派員」として鑑賞レポートを書いて発信!
ぜひご覧ください。(原文のまま、書き起こしています。)
***************************************
小金井市立小金井第二小学校 5年 加藤百華
MaNGROVEとは?
挾間美帆さん(ジャズ作曲家)と小金井出身の滝千春さん(世界的ヴァイオリニスト)が立ち上げたプロジェクト「MaNGROVE」の意味
Man(人)が紡ぐ(Groovy)な音楽を紡ぎたいと思いが込められている
【第1部】※
第1部の最初の「introduction」はたぶん同じようなせんりつがちょっとだけくりかえされていた。また強く、弱く、強く、弱く、と強いところと弱いところがくりかえされている部分などがあった。2曲目の「Dance of Knights」では、ピアノとチェロはなしでえんそうされていた。テンポがはやい曲でのばすところが多かった。自分はちょっと悲しめな音楽かなと思いました。3曲目の「Romeo and Juliet」はピアノはひくい音がおおかったです。ひくい音から高い音になったりのくり返しなどがあった。とちゅうでほんのすこし、ちょっぴり、頭をこくこくうごかして、テンポにたぶんのっているお客さんがいた。4曲目の「Death of Tybolt」ではコントラバスの人とピアノの人とチェロのえんそう者のかたたちが合わせてひくい音をえんそうしていました。5曲目の「Romeo at the Grave of Juliet」はさいしょはテンポがはやく、とちゅうゆっくりになったり、はやくなったりのくりかえしのさがはげしい曲だった。
【第2部】※
第2部の最初の1曲目の曲ではヴァイオリンの2人だけでえんそうしていた。音ていの差がはげしかったり、テンポがすごくはやかったりしていました。はげしい曲でした。えんそうしゃの人たちはものすごくはやいときはひざをまげたりのばしたりしながらえんそうしていました。2きょくめはさいしょはおだやかでとちゅうから音がいきなり強くなっていたりしていた。ピアノはとちゅうで同じおんていのところがあった。3きょくめはさいしょはピアノだけでとちゅうからほかのがっきがえんそうをはじめていた。のばしたり、はやくえんそうしていた。
4曲目は音が強い曲でテンポがはやかった。
5曲目はとちゅうからえんそう者の人たちがゆかを足でとんとんたたいてえんそうしていた。のばすところがおおかった。
感想
・えんそう者の人たち(MaNGROVE)はいきなり強くなって弱くなったりテンポがはやい曲でもどうどうとまちがえずにひけていてすごいなと思いました。
・えんそう者の人たちはテンポがものすごくはやかったりするときにひざなどまげたりのばしたりしてえんそうしていたりしていた。
・工夫していたところはヴァイオリンの人とかは同じヴァイオリンの人と目であいずをしてえんそうしてて、そういうふうに工夫しているんだなと思いました。
・同じようなせんりつがくりかえされている曲がたくさんありました。
(公演写真:横田敦史)
***************************************
曲の流れや演奏者の動きに注目した加藤さん。
その観察力から、演奏者のすごさに驚いた様子がよく伝わってくるレポートです。
★スタッフによるイベントレビューは【こちら】
|
【こがねいジュニア特派員レポート vol.24】 挾間美帆 & 滝 千春 project MaNGROVE |
26. 01. 29 |
市内の小学生が「こがねいジュニア特派員」として鑑賞レポートを書いて発信!
ぜひご覧ください。(原文のまま、書き起こしています。)
***************************************
挾間美ほ & 滝 千春 MaNGROVE
小金井市立前原小学校 5年 佐野 笙
2026.1.17(土)
マングローブ
海水と川の水が混ざる場所に生える、塩に強い特しゅな木の森
体を支える根元にカニやハゼが生息し、そこにほ乳類や鳥類が集まり、海水に浸かる場所が、魚や小さな生物の隠れ場所になる。
Man「人」とGroove「ノリ」(気分が高まって身体が自然と動き出す)
このタイトルを見て、すてきな空間に世界からいろんな人が集まって、楽しい音楽が奏でられるんだと、楽しみになった。
開場ギリギリまでリハーサル。ぶ台そで(上手)、小さな窓から、ぶ台の様子が見えた。6人の演奏者のこ吸が合っていて、テンポやリズムが心地良くて、自然と体が動いた。
11月の連合音楽会で、ぶ台に上がった時と、今回のコンサートとぶ台が全くちがってみえた。滝さんと挾間さんが、曲を説明してくれて、イメージが作れた。
CHIMERA「キメラ」
頭がライオン、胴体ヤギ、尾がヘビの火を吹く怪物。
もう一つの意味として、一つの個体内に異なる「い伝子」を持つ細胞。
ヴァイオリン2人、ヴィオラ、チェロの弦楽四重奏
勢いよく演奏が始まった。4人の動きがはげしくて、音が細かくてせん細だったのが不思議な音楽だった。
挾間さんと滝さんは、赤い衣装で、とてもかっこ良かった。
リハーサルの時と全員、服がちがった。
プロコフィエフのイントロダクション
曲中、ずっと鳴り続く音が聞こえた。わざとひびかせていると思っていたが、2曲目「き士たちのおどり」に入る前、挾間さんが、電子音に気づき、「私、絶対音感があって」と言いながら、会場に鳴っている電子音と同じ音をピアノで弾いていてビックリした。挾間さんは耳がいいんだなぁと思った。
ハプニングも、生のコンサートならではだと思った。
「き士たちのおどり」は、ぼくも知っている曲で、低音のコントラバスやピアノが大地をふむような迫力が合わさっていた。付点のリズムが上下するヴァイオリンと、と中から挾間さんの編曲になって、どんどん音が複雑にからみ合っていって、ちがう世界につれていかれた。
これが、JAZZってものなのか、ふ段、聞くことがない音があふれていた。
B↔C
Bはバッハ400年前の音楽、Cはコンテンポラリーが行ったり来たりする。Bはドイツ音楽でシ、Cはドで「シ」と「ド」を行ったり来たりする。シとドはとなり合った音で、どう音楽が作られていくのかと思ったが、自分が考えていた以上に沢山の音がふくまれていた。
「Space in Senses」
Parallelism 平行
少ない音から始まり、どんどん増えて、また最後は減っていく音楽だった。同じ音の動きが一緒に並んで進んでいるのがよく分かったし、きれいだった。3拍子と4拍子が交互に出てくる。ちょっと変わった感じがした。
Big Dipper 北斗七星
♩♫♩♫♫♫‿♩の7拍のリズムがくり返されて、ピアノと弦楽器が音楽で会話している感じ。
くり返しながらどんどん変化して、聞いていて楽しかった。
ミッションインポッシブルみたいに、ドキドキ、きん張感がある、美しいメロディーで6人の息がピッタリ合っていて、かっこ良かった。
アンコール曲はリハーサルでぶ台そでで、きいていた曲だった。
ぼくは、ドラムを習っているけれど、演奏中、手で楽器を叩いたり、足をふみならして、音を出していて、身体全部で音楽を演奏していてすごいと思った。6人が楽しんで演奏しているのが伝わってきた。ぼくも、自然と体がグルーヴした。
(公演写真:横田敦史)
***************************************
ドラムを習っている佐野さんならではの、音楽の感じ方やその表現が見事です。
開演前にのぞいた時のリハーサルの様子や、途中のトークで聞いた曲目解説からイメージしたイラストも描いてあり、とても読み応えのあるレポートです。
★スタッフによるイベントレビューは【こちら】
|
【こがねいジュニア特派員レポート vol.23】 フラメンコギター・デュオ 徳永兄弟 ライブ with パルマ&ダンス・カンテ |
25. 12. 20 |
市内の小学生が「こがねいジュニア特派員」として鑑賞レポートを書いて発信!
ぜひご覧ください。(原文のまま、書き起こしています。)
***************************************
小金井市立緑小学校 3年 小池優真
1曲目の「イントロ」は、徳永兄弟2人のギターで始まり、いきなり大きな音になって2人の息が合わさって楽しかった。カンテの人は声の強弱があり難しそうだなと思った。
3曲目の「スペイン」は最初から色々な音になってかっこよかった。背景の照明が大阪万博の大屋根リングをつくった「藤本壮介さん」の建築物のようで綺麗だと思った。
5曲目の「赤とんぼ」のカバーは小さな優しい音から始まって途中から激しくなり、足でリズムを刻む二人の息が合わさり、1番かっこよかった。
休憩を挟んで後半1曲目の「アレグリアス」。ギターに合わせてフラメンコダンスの人が難しそうなタップをしてそれに合わせてみんなで息をあわせてひくところが感動した。
後半2曲目の「ファルーカ」はだんだん音が早く激しくなって元気が出て気持ちの良い曲だった。
後半3曲目の「アスーカル モレーノ」は、4拍子の最初から激しい曲で踊りたくなるような曲だった。
アンコールのリベルタンゴは、弾いている人も聴いている人も笑顔で明るく楽しい曲で面白かった。楽器によって、曲の雰囲気がこんなに違うんだと思った。
皆が息をあわせて1つの作品を作り上げていた。パーカッションの人はスティックや手を使って音を出していたし、カンテの人は徳永兄弟のリズムをとってそのリズムに合わせて歌を歌っていた。タップダンスの人はみんなの前で4人のリズムに合わせて堂々と踊っていた。
皆が息をあわせて11曲を作り上げていてかっこいいなと思った。
(公演写真:横田敦史)
***************************************
「皆が息をあわせて1つの作品を作り上げていた」と、
演奏の詳細が伝わってくるレポートを書いてきてくれた小池さん。
その文章と絵から、フラメンコの音色が聴こえてくるようです。
★スタッフによるイベントレビューは【こちら】
|
【こがねいジュニア特派員レポート vol.22】 フラメンコギター・デュオ 徳永兄弟 ライブ with パルマ&ダンス・カンテ |
25. 12. 20 |
市内の小学生が「こがねいジュニア特派員」として鑑賞レポートを書いて発信!
ぜひご覧ください。(原文のまま、書き起こしています。)
***************************************
小金井市立小金井第一小学校 3年 青山紘大
徳永兄弟 すごい演奏をありがとうございます!!!
(公演写真:横田敦史)
***************************************
満席の大ホールで演奏をしているメンバーの絵を書いてきてくれた青山さん。
スポットライトの感じや演奏者の表情がとても素敵です。
終演後のサイン会でも徳永兄弟をずっと見ていた青山さんの微笑ましい姿に、
スタッフも笑顔になりました。
★スタッフによるイベントレビューは【こちら】
|
【こがねいジュニア特派員レポート vol.21】 はけの森美術館 展覧会《中村研一とモダニズム》 |
25. 12. 11 |
市内の小学生が「こがねいジュニア特派員」として鑑賞レポートを書いて発信!
ぜひご覧ください。(原文のまま、書き起こしています。)
***************************************
小金井市立小金井第一小学校 1年 U.K
十一月二十九日(土)に「はけのもりびじゅつかん」で中むらけん一さんのてんらんかいを見ました。
一ばんすきなえ。
わたしが一ばんすきだったのは「こねこ」(一九五一ねん)というえです。ねこがすきなきもちがつたわるからです。
けん一さんは ねこをかっていたと びじゅつかんの人がおしえてくれました。
わたしも「こねこ」のえをかきました。
けん一さんの「こねこ」をまねして、えをかきました。アクリルえのぐをつかいました。けん一さんのえとは、いろもちがってかたちもちがうけれどイメージしてかきました。
がくもつくりました。
けん一さんの「こねこ」のえは すてきながくにはいっていたので がくもつくりました。かぞくといっしょにつくりました。
ぜひけん一さんの「こねこ」をびじゅつかんで見てください。
***************************************
「こねこ」の絵からインスピレーションを得て、素敵な絵と立派な額縁を作成してくれました。
レポートも色使いがよく、とても読みやすかったです。
小金井市立「はけの森美術館」では、現在企画展を開催中!
■中村研一とモダニズム 第二期 モダニズム、変容
【会期】2025年10月31日(金)~12月21日(日)
https://www.hakenomori-art-museum.jp/
|
【こがねいジュニア特派員レポート vol.20】 はけの森美術館 展覧会《中村研一とモダニズム》 |
25. 12. 11 |
市内の小学生が「こがねいジュニア特派員」として鑑賞レポートを書いて発信!
ぜひご覧ください。(原文のまま、書き起こしています。)
***************************************
はけの森美じゅつ館
小金井市立小金井第三小学校 4年 秋田大晴
十一月二十九日にはけの森美じゅつ館に行きました。
美じゅつ館には中村研一さんの作品がかざってありました。中村研一さんの作品はぜんぶすごかったけど、ぼくがとくに気にいったのは「中村正奇氏の肖像」です。
すごく表じょうやかげのかきかたがうまかったです。1929年にかいた肖像画と1950年代の肖像画をくらべてみると、ちがいがありました。はじめにかいたのは戦争で国民にゆう気をつけるために、とてもかっこよく強そうにかいていたけど、あとにかいたほうは、戦争が終わって人やねこや色なども、やさしいふんいきになっていました。中村研一さんは、絵と、生活や時代をつなげてかいていてすごいと思いました。もっと中村研一さんのことを知りたいと思いました。
***************************************
大晴さんは、作家さんの絵を通じて、戦争前と戦争後の心の移り変わりを見つけてくれました。
描いてくれたイラストもとても分かりやすかったです。
ぜひ、またはけの森美術館に見に来てください。
小金井市立「はけの森美術館」では、現在企画展を開催中!
■中村研一とモダニズム 第二期 モダニズム、変容
【会期】2025年10月31日(金)~12月21日(日)
https://www.hakenomori-art-museum.jp/
|
【こがねいジュニア特派員レポート vol.19】 はけの森美術館 展覧会《中村研一とモダニズム》 |
25. 12. 11 |
市内の小学生が「こがねいジュニア特派員」として鑑賞レポートを書いて発信!
ぜひご覧ください。(原文のまま、書き起こしています。)
***************************************
かんたいにゅうこう
小金井市立小金井第三小学校 2年 秋田野晴
11月29日土曜日に、はけの森びじゅつかんに行きました。
中村研一さんがかいた絵がいっぱいありました。ヨヨギというばしょにあった家がせんそうでなくなってしまったので、小金い市のハケらへんにすんでいたそうです。
ふね、人、けしき、ねこ、いろいろな絵がありました。えんぴつ、絵の具、すみをつかった絵がいっぱいありました。中でも、一番気に入ったのは、船と、海と、岩の絵です。名前は、「かんたいにゅうこう」です。どこが気に入ったかというと、太ようの光のさいげんがすごかったからです。岩のかげとかも黒色を入れたりしてて、よかったです。海は水色に白色をまぜたりして、きれいでした。船がとおった後のなみがあって船が早いかんじがしました。こんなにきれいな絵なのに、ぐんかんだと知ってちょっとせつない気もちになりました。
***************************************
展示されている絵の題材や材料まで、細部にわたってよく見てくれた野晴さん。
美しい絵の中に隠れた現実に思いをめぐらし、違う切り口から観察する力に感心しました。
小金井市立「はけの森美術館」では、現在企画展を開催中!
■中村研一とモダニズム 第二期 モダニズム、変容
【会期】2025年10月31日(金)~12月21日(日)
https://www.hakenomori-art-museum.jp/
|
【こがねいジュニア特派員レポート vol.18】 宇崎竜童 弾き語りLIVE 2025 ~JUST GUITAR JUST VOCAL~ |
25. 11. 26 |
市内の小学生が「こがねいジュニア特派員」として鑑賞レポートを書いて発信!
ぜひご覧ください。(原文のまま、書き起こしています。)
***************************************
宇崎竜童 弾き語りLIVE 2025 JUST GUITAR JUST VOCAL
小金井市立小金井第二小学校 4年 林田和佳南
Profile
1973年に「ダウン・タウン・ブギウギ・バンド」を、結成しています。来年の2月に80さいになると話していました。
ヒット曲:「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」「スモーキンブギ」などなど
山口百恵さんに提供した曲:「プレイバックPart2」、「さよならの向う側」などなど...
心に残った曲
アンコール曲を含め、18曲の中で特に心に残った曲は、
1曲目:「港のヨーコ・ヨコハマ・ヨコスカ」、5曲目:「イミテイション・ゴールド」
14曲目:「OIRA JAPANESE BANDMAN」(ちょっとラップっぽい)の3曲です。
知っている曲は少なかったけれど、楽しかったです。
セット
「スモークマシーン」という機械を使っているらしく、うすい煙のようなものが出ていました。照明は、曲のふんいきにあわせて、色や光の強さを変えていました。
ギター&トランペット
ギターは7本もありました。曲ごとにギターをかえていて、すごいと思いました。
1つだけ.銀色のトランペットがありました。とてもきれいな音がひびきました。
感想
MCで、私でもわかりやすいトークで、楽しかったです。79さいとは思えないほどいい声でした。
また、竜童さんをよんでください。
(公演写真:横田敦史)
***************************************
林田さんは、スタッフによる公演前の話しや公演中の感想を、
しっかりとしたレポートにまとめてきてくれました。
宇崎さんの似顔絵や、糸を使った臨場感あふれるギターの貼り絵もすてきです!
★スタッフによるイベントレビューは【こちら】


