
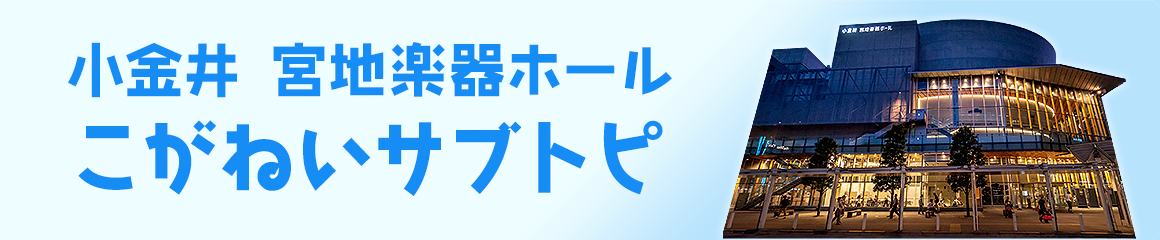
20. 12. 26
イベントレポート【FOCUS こがねい】津村禮次郎の能楽の楽しみ
12月6日(日)当館主催では初となる能楽の公演を、小金井市が誇る能楽師、津村禮次郎プロデュースにより開催しました。
「能ってなんか難しそう・・」と敬遠してきた方にこそ足を運んでもらいたい、能の楽しさをお伝えしたい!と、冒頭にミニ能楽講座を設けました。
能・狂言の歴史、今回のあらすじや見せ場となる場面での小道具の役割、謡(うたい)の解釈などを解説し、これから始まる古典芸能の世界へと期待が高まります。


能楽では、能と狂言がセットで上演されます。解説の後は、まずは狂言師・野村万蔵さん、野村万之丞さん、野村晶人さんが登場。棒に縛られながらも、何とかして酒を飲もうとするコミカルな狂言『棒縛(ぼうしばり)』を披露しました。
狂言ならではのリズムある言い回し、大胆でありつつ細やかな表情や美しく可笑しみのある所作に、客席からは笑いがこぼれます。



後半は、能『葵上』です。
源氏物語の「夕顔」、「葵」の巻を大胆に能に作りこんだ代表的な作品で、最も人気がある能の演目の一つ。演目名にもなっている「葵上」は人物としては登場せず、舞台中央に置かれた美しい小袖が病に伏せる葵上を表します。
光源氏を廻る女性の中でも、深く光源氏に心を寄せていた六条御息所。嫉妬心に苛まれ、葵上のために巫女が祈祷を始めると、生き霊となり葵上を幽界へと連れ去ろうとします。
ここで用いられているのは「泥眼(でいがん)」と呼ばれる能面。髪が乱れているのも多く、嫉妬に苦しむ女性やこの世のものではないものをあらわす虚ろな目が特徴です。
どことなく漂う薄気味悪さ。客席にも少し緊張が走ります。


そして、怨霊を鎮めるために比叡山からの横川の行者が祈りを捧げ始めると、怨霊は真の鬼と化します。
激しい憎しみと妖艶さを表す真っ赤な袴、恐ろしい形相の「般若(はんにゃ)」の能面をつけて舞台上へあらわれます。


行者を激しく威嚇する鬼、いさめようとする行者。お囃子や謡も大きくなり、両者の争いもピークに!
凄まじい争いの末、六条御息所は遂に仏の心を得たとして一曲を結び、舞台上には静寂が訪れるのでした。


ご来場いただいた方からは、「初めてだったけど解説があったので楽しめた」「幽玄の世界を堪能した」などのお声をいただき、普段のホールとはまた違った舞台の魅力を感じていただけました。
こちらのブログを読んでくださっている方に特別に、今回の舞台裏を少しだけ公開!
能の舞台には所作台(しょさだい)と呼ばれる特別な舞台を設置します。所作台は、足袋でのみ歩くことが許されるとても神聖な場所。舞台スタッフも皆足袋を履き、橋掛かりの位置や背景の竹の長さなどを入念にチェックします。

能の舞台上では、場面に合わせて衣装の早着替えが必要です。そのため、舞台袖には鏡などが設置され、小さな楽屋に変身。後見(こうけん)と呼ばれるお支度を整える役割の人が、能面をつけるとほぼ前が見えないシテ方を舞台上へ送り出し、手際よく着替えさせるその鮮やかな仕事ぶりに、初めて能の舞台裏を体験した担当は感動しました。
また、背景に使われた竹の装飾は、前夜に小金井市内の造園の職人さんが舞台上で竹を割って手作りした一点もの!ライトアップされた竹の装飾は、今回の舞台の世界観を表していてとても素敵でした。

ご来場いただいた方、ブログをお読みいただいた方、どうもありがとうございました!
公演写真:藤本史昭
![]() 最新の書き込み
最新の書き込み
【こがねいジュニア特派員レポート vol.17】
こがねいガラ・コンサート2025
【こがねいジュニア特派員レポート vol.16】
こがねいガラ・コンサート2025
【こがねいジュニア特派員レポート vol.15】
こがねいガラ・コンサート2025
【こがねいジュニア特派員レポート vol.14】
Center line art festival Tokyo 2025 《共催》
【こがねいジュニア特派員レポート vol.13】
第25回 こがねい落語特選 <納涼>風鈴にソーダ水の会
【こがねいジュニア特派員レポート vol.12】 夏休み木工チャレンジ2025《共催》
【こがねいジュニア特派員レポート vol.11】 夏休み木工チャレンジ2025《共催》
【こがねいジュニア特派員レポート vol.10】 夏休み木工チャレンジ2025《共催》
![]() 月別アーカイブ
月別アーカイブ
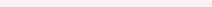 |
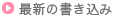  |
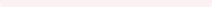 |
 |
|
〒184-0004
東京都小金井市本町6-14-45 TEL: 042-380-8077 FAX: 042-380-8078 開館時間: 9:00 ~ 22:00 受付時間: 9:00 ~ 19:00 休館日: 毎月第2火曜日および第3火曜日(祝日の場合はその直後の平日) / 年末年始 / 保守点検日 |
 |
|
イベントレポート 【FOCUS こがねい】津村禮次郎の能楽の楽しみ |
20. 12. 26 |
12月6日(日)当館主催では初となる能楽の公演を、小金井市が誇る能楽師、津村禮次郎プロデュースにより開催しました。
「能ってなんか難しそう・・」と敬遠してきた方にこそ足を運んでもらいたい、能の楽しさをお伝えしたい!と、冒頭にミニ能楽講座を設けました。
能・狂言の歴史、今回のあらすじや見せ場となる場面での小道具の役割、謡(うたい)の解釈などを解説し、これから始まる古典芸能の世界へと期待が高まります。


能楽では、能と狂言がセットで上演されます。解説の後は、まずは狂言師・野村万蔵さん、野村万之丞さん、野村晶人さんが登場。棒に縛られながらも、何とかして酒を飲もうとするコミカルな狂言『棒縛(ぼうしばり)』を披露しました。
狂言ならではのリズムある言い回し、大胆でありつつ細やかな表情や美しく可笑しみのある所作に、客席からは笑いがこぼれます。



後半は、能『葵上』です。
源氏物語の「夕顔」、「葵」の巻を大胆に能に作りこんだ代表的な作品で、最も人気がある能の演目の一つ。演目名にもなっている「葵上」は人物としては登場せず、舞台中央に置かれた美しい小袖が病に伏せる葵上を表します。
光源氏を廻る女性の中でも、深く光源氏に心を寄せていた六条御息所。嫉妬心に苛まれ、葵上のために巫女が祈祷を始めると、生き霊となり葵上を幽界へと連れ去ろうとします。
ここで用いられているのは「泥眼(でいがん)」と呼ばれる能面。髪が乱れているのも多く、嫉妬に苦しむ女性やこの世のものではないものをあらわす虚ろな目が特徴です。
どことなく漂う薄気味悪さ。客席にも少し緊張が走ります。


そして、怨霊を鎮めるために比叡山からの横川の行者が祈りを捧げ始めると、怨霊は真の鬼と化します。
激しい憎しみと妖艶さを表す真っ赤な袴、恐ろしい形相の「般若(はんにゃ)」の能面をつけて舞台上へあらわれます。


行者を激しく威嚇する鬼、いさめようとする行者。お囃子や謡も大きくなり、両者の争いもピークに!
凄まじい争いの末、六条御息所は遂に仏の心を得たとして一曲を結び、舞台上には静寂が訪れるのでした。


ご来場いただいた方からは、「初めてだったけど解説があったので楽しめた」「幽玄の世界を堪能した」などのお声をいただき、普段のホールとはまた違った舞台の魅力を感じていただけました。
こちらのブログを読んでくださっている方に特別に、今回の舞台裏を少しだけ公開!
能の舞台には所作台(しょさだい)と呼ばれる特別な舞台を設置します。所作台は、足袋でのみ歩くことが許されるとても神聖な場所。舞台スタッフも皆足袋を履き、橋掛かりの位置や背景の竹の長さなどを入念にチェックします。

能の舞台上では、場面に合わせて衣装の早着替えが必要です。そのため、舞台袖には鏡などが設置され、小さな楽屋に変身。後見(こうけん)と呼ばれるお支度を整える役割の人が、能面をつけるとほぼ前が見えないシテ方を舞台上へ送り出し、手際よく着替えさせるその鮮やかな仕事ぶりに、初めて能の舞台裏を体験した担当は感動しました。
また、背景に使われた竹の装飾は、前夜に小金井市内の造園の職人さんが舞台上で竹を割って手作りした一点もの!ライトアップされた竹の装飾は、今回の舞台の世界観を表していてとても素敵でした。

ご来場いただいた方、ブログをお読みいただいた方、どうもありがとうございました!
公演写真:藤本史昭



